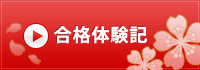現役合格おめでとう!!
2025年 大泉学園校 合格体験記

東京大学
文科一類
文科一類
鈴木遊 くん
( 大泉高等学校 )
2025年 現役合格
文科一類
中2から数学特待生として入学しました。僕がなんとか合格できた1番大きな要因は、東進での受講だと思います。青木純二先生や林修先生など、各教科に対する僕たち生徒の世界観を根底から覆すような優秀な講師陣による授業が、一時停止可能な映像による授業という形で受けられるため、理解の度合いに応じて、自身で噛み砕くことができるまで時間をかけることも、先取りを進め続けることもできます。この仕組みでの受講が低学年時には先取りとして役立ち、受験期には深い理解につながりました。
また、低学年時から模試を受けていたため、試験場特有の雰囲気や時間配分にある程度慣れており、試験本番の緊張や失敗の中でも自分の普段通りの解法を見失わずにいることができたことも大きかったと思います。それだけでなく、高2、高3の東大模試でA判定を取り続けられたことは、時に慢心することにつながりもしましたが、受験期の最後の最後に、漠然とした不安に駆られる自分を落ち着かせ、自分を信じて本番に臨むことができた一因でもあると思っています。
勉強そのものも大切ですが、多くの人が言う通り、いざ受験が始まった時に肝要だったのは健康管理だと思います。風邪でも引いて勉強できない日が生まれることは他の受験生、理想の自身の状態に遅れをとることになります。僕は朝6時起床、夜10時就寝を守り抜いた上で昼寝などもして、睡眠時間だけは削らないようにしていました。短いようで長く、長いようで短かった受験を長期的な視点を持って健康なままで乗り越えられたことは、受験期で自分が1番良くできたことだなと思います。
また、低学年時から模試を受けていたため、試験場特有の雰囲気や時間配分にある程度慣れており、試験本番の緊張や失敗の中でも自分の普段通りの解法を見失わずにいることができたことも大きかったと思います。それだけでなく、高2、高3の東大模試でA判定を取り続けられたことは、時に慢心することにつながりもしましたが、受験期の最後の最後に、漠然とした不安に駆られる自分を落ち着かせ、自分を信じて本番に臨むことができた一因でもあると思っています。
勉強そのものも大切ですが、多くの人が言う通り、いざ受験が始まった時に肝要だったのは健康管理だと思います。風邪でも引いて勉強できない日が生まれることは他の受験生、理想の自身の状態に遅れをとることになります。僕は朝6時起床、夜10時就寝を守り抜いた上で昼寝などもして、睡眠時間だけは削らないようにしていました。短いようで長く、長いようで短かった受験を長期的な視点を持って健康なままで乗り越えられたことは、受験期で自分が1番良くできたことだなと思います。

東京大学
文科三類
文科三類
森本晴信 くん
( 大泉高等学校 )
2025年 現役合格
文科三類
僕は高校3年の4月初めまで、吹奏楽部に所属していました。学生指揮者を務め、習い事もせず部活一筋で取り組んでいました。当時から東大を目指してはいたものの、東進に入学したのは高校3年の4月末でした。それ以前も大学受験のための勉強をしていたわけでもなく、他の東大志望者に比べると遅いスタートでした。ただ、当時から共通テスト本番レベル模試ではA判定、記述模試ではC判定を取っていて、焦燥感のようなものはあまり感じていませんでした。
東進には東大対策の映像による授業があって、僕はそれらを重点的に取りました。どれもとても充実した内容で、非常におすすめしたいものの1つです。中でも、青木純二先生の「数学の真髄」シリーズは、高校の授業で習うような数学しか対処できなかった僕でも非常にわかりやすかったです。
受講と並行して、6月ごろから過去問を始めました。東進では、東大の過去問だけではあるのですが、答案の採点が直近25ヵ年の過去問まで利用可能でした。東大の入試は英語の一部を除いてすべて記述で、自己採点では正確な点数が把握しにくいです。東大の入試をしっかりと理解している人に採点をしてもらうことは、自身が現在どのくらいの得点力を持っているのかを知ることができるだけでなく、答案を作成するにあたってのポイントなどを理解することができました。東大志望者には25か年の過去問演習講座をとることを強くおすすめします。
7月末に受講がすべて終了し、8月は過去問を5年分取り組み、初めての東大模試に挑みました。東進の東大模試は、東大らしい問題がでるので、おすすめできるものだと思います。参加人数は少ないですが、比較的実力に見合った点数が出やすい模試だと思います。東進による東大模試は東大入試における自身の得点力の絶対評価がしやすい、といえるでしょう。
9月に入って追加で講座をとり、それらの講座に取り組みながらも東大の過去問を進めました。10月の東大本番レベル模試では、記述模試で初めてA判定をとりました。しかし、その後も東大の過去問ばかりやっていたところ、12月の共通テスト本番レベル模試でB判定をとり、かなり危機感を持って、本番までの3週間ほど共通テスト対策を行いました。このおかげで、本番ではかなり高得点をとることができました。
結局、東大入試本番までに、苦手かつ嫌いであった国語は17年、得意だった英語は10年、好きだった数学と地理と世界史は27年過去問を解きました。どれも直近3~10年は2回演習を行いました。
担任助手の方との面談や東進特有のチームミーティングには、精神的な部分でかなり助けてもらったと思います。担任助手の方やチームの仲間とはとても親しく、様々な悩みを打ち明けていました。僕はかなり打たれ弱い性格で、おそらく1人では受験勉強を続けてこれなかったと思うので、こういった精神的な面において、「受験は団体戦」という言葉はある程度言いえて妙であるように思います。
最後に、東大に選ばれたからには、僕には、今後さらに勉学に励み、ゆくゆくは日本を、そして世界を引っ張っていく義務があると感じます。そのためにも、決して現状に満足することなく、日本トップクラスの頭脳を持つ新たな仲間たちと切磋琢磨して行こうと思います。
東進には東大対策の映像による授業があって、僕はそれらを重点的に取りました。どれもとても充実した内容で、非常におすすめしたいものの1つです。中でも、青木純二先生の「数学の真髄」シリーズは、高校の授業で習うような数学しか対処できなかった僕でも非常にわかりやすかったです。
受講と並行して、6月ごろから過去問を始めました。東進では、東大の過去問だけではあるのですが、答案の採点が直近25ヵ年の過去問まで利用可能でした。東大の入試は英語の一部を除いてすべて記述で、自己採点では正確な点数が把握しにくいです。東大の入試をしっかりと理解している人に採点をしてもらうことは、自身が現在どのくらいの得点力を持っているのかを知ることができるだけでなく、答案を作成するにあたってのポイントなどを理解することができました。東大志望者には25か年の過去問演習講座をとることを強くおすすめします。
7月末に受講がすべて終了し、8月は過去問を5年分取り組み、初めての東大模試に挑みました。東進の東大模試は、東大らしい問題がでるので、おすすめできるものだと思います。参加人数は少ないですが、比較的実力に見合った点数が出やすい模試だと思います。東進による東大模試は東大入試における自身の得点力の絶対評価がしやすい、といえるでしょう。
9月に入って追加で講座をとり、それらの講座に取り組みながらも東大の過去問を進めました。10月の東大本番レベル模試では、記述模試で初めてA判定をとりました。しかし、その後も東大の過去問ばかりやっていたところ、12月の共通テスト本番レベル模試でB判定をとり、かなり危機感を持って、本番までの3週間ほど共通テスト対策を行いました。このおかげで、本番ではかなり高得点をとることができました。
結局、東大入試本番までに、苦手かつ嫌いであった国語は17年、得意だった英語は10年、好きだった数学と地理と世界史は27年過去問を解きました。どれも直近3~10年は2回演習を行いました。
担任助手の方との面談や東進特有のチームミーティングには、精神的な部分でかなり助けてもらったと思います。担任助手の方やチームの仲間とはとても親しく、様々な悩みを打ち明けていました。僕はかなり打たれ弱い性格で、おそらく1人では受験勉強を続けてこれなかったと思うので、こういった精神的な面において、「受験は団体戦」という言葉はある程度言いえて妙であるように思います。
最後に、東大に選ばれたからには、僕には、今後さらに勉学に励み、ゆくゆくは日本を、そして世界を引っ張っていく義務があると感じます。そのためにも、決して現状に満足することなく、日本トップクラスの頭脳を持つ新たな仲間たちと切磋琢磨して行こうと思います。

京都大学
工学部
物理工学科
脇阪みやび くん
( 大泉高等学校 )
2025年 現役合格
工学部
僕はこの合格体験記において以下の3つのことを述べようと思います。1つは僕が東京在住ながら京都大学に至ったいきさつ、2つ目は受験生活について、3つ目は学習面についてです。
僕は京都にしかない伝統、自然、建物、人、思想、それら全部をひっくるめた京都という町の雰囲気と、「なんか面白そう」な学校の在り方に魅かれて京都大学を第1志望にしました。僕は高1の8月から高2の6月ごろまで10か月ほどアメリカに留学していたのですが、帰ってきてから東京に何か堅苦しさを感じて、東京で生きるのが息苦しいと感じていました。これは僕の偏見かもしれませんが、動画を見たり実際に京都に足を運んだりして、僕は京都、あるいは京都大学は、東京ほど周りを気にすることで生じる障壁のようなものがない、「Be yourself」を貫ける場所であると感じました。また祖父母の家が京都にあり、京都という町にゆかりがあったことも、京大を目指し始めたきっかけの1つです。加えて、僕は将来宇宙系の職業か研究をしたいと考えているのですが、同時に哲学にも興味があって、高3の春には、僕には哲学にゆかりがあり、日本をリードする宇宙研究に触れられるのは京都大学しかない、という風に感じるようになりました。皆さんも、志望校はレベルや自分の苦手教科、周りに左右されることなく、自分が本気で行きたいと思うところに決めることを心からお勧めします。
僕はおそらく過去の京大模試の国語で4割以上得点できたことはほとんどないし、共通テストの国語も10月あたりに105点くらいの点数をたたき出したような記憶があります。何かしらの苦手教科はあって然りのものなので、絶対にこの大学に行く/行けるという気概を持って戦略を練ることをお勧めします。僕は、「京大の問題だけは絶対に解けるようになる!京大の問題さえ解ければ勝ち!」と信じて突き進みました。それだけ僕が京都大学にかける思いは大きかったです。
次に、受験生としての生活について。まず生活面では、自分に合ったスタイルを見つけてそれを実行するのはもちろんですが、睡眠時間だけは確保していました。僕は朝型だったので、夏休みは毎日20時45分には東進を出て帰宅の道を辿っていました。そして22時30分くらいには寝て、6時ちょうどに起きるという感じでした。2月の国公立直前期には、焦燥感から睡眠時間は7時間ピッタリくらいにまで落ちたのですが、基本的には最低7時間半から8時間は睡眠をとっていたと思います。その分集中できるときに他の人より集中しよう、というのが僕の勉強のスタンスでした。また、僕は高3の6月中旬までは部活動を続けて、引退後も夏休みに入るまではちょくちょく運動していました。僕の場合、運動は持久力を鍛えたり自分をポジティブな気分にさせたりしてくれるものだと思っていたので、いい気分転換として、時間がない時も少し散歩するなどしていました。
最後に3つ目の学習面について。僕が最も大切にしていたことは考え抜くことです。直前期はたくさん問題演習することも大切だと思いますが、そうでないときは基本解けるまで、あるいは分かるまでは時間無制限で徹底的に考え抜くように心がけていました。1問の数学の問題に1日を費やした時もありました。しかし、このようにして考え抜いた結果、分かるという状態に達したその経験や喜びは、自分の身体感覚の1部として自信と糧にかわり、問題を解く力となったような気がします。受動的にではなく、能動的に行動することが合格に繋がったように僕は思います。
僕は京都にしかない伝統、自然、建物、人、思想、それら全部をひっくるめた京都という町の雰囲気と、「なんか面白そう」な学校の在り方に魅かれて京都大学を第1志望にしました。僕は高1の8月から高2の6月ごろまで10か月ほどアメリカに留学していたのですが、帰ってきてから東京に何か堅苦しさを感じて、東京で生きるのが息苦しいと感じていました。これは僕の偏見かもしれませんが、動画を見たり実際に京都に足を運んだりして、僕は京都、あるいは京都大学は、東京ほど周りを気にすることで生じる障壁のようなものがない、「Be yourself」を貫ける場所であると感じました。また祖父母の家が京都にあり、京都という町にゆかりがあったことも、京大を目指し始めたきっかけの1つです。加えて、僕は将来宇宙系の職業か研究をしたいと考えているのですが、同時に哲学にも興味があって、高3の春には、僕には哲学にゆかりがあり、日本をリードする宇宙研究に触れられるのは京都大学しかない、という風に感じるようになりました。皆さんも、志望校はレベルや自分の苦手教科、周りに左右されることなく、自分が本気で行きたいと思うところに決めることを心からお勧めします。
僕はおそらく過去の京大模試の国語で4割以上得点できたことはほとんどないし、共通テストの国語も10月あたりに105点くらいの点数をたたき出したような記憶があります。何かしらの苦手教科はあって然りのものなので、絶対にこの大学に行く/行けるという気概を持って戦略を練ることをお勧めします。僕は、「京大の問題だけは絶対に解けるようになる!京大の問題さえ解ければ勝ち!」と信じて突き進みました。それだけ僕が京都大学にかける思いは大きかったです。
次に、受験生としての生活について。まず生活面では、自分に合ったスタイルを見つけてそれを実行するのはもちろんですが、睡眠時間だけは確保していました。僕は朝型だったので、夏休みは毎日20時45分には東進を出て帰宅の道を辿っていました。そして22時30分くらいには寝て、6時ちょうどに起きるという感じでした。2月の国公立直前期には、焦燥感から睡眠時間は7時間ピッタリくらいにまで落ちたのですが、基本的には最低7時間半から8時間は睡眠をとっていたと思います。その分集中できるときに他の人より集中しよう、というのが僕の勉強のスタンスでした。また、僕は高3の6月中旬までは部活動を続けて、引退後も夏休みに入るまではちょくちょく運動していました。僕の場合、運動は持久力を鍛えたり自分をポジティブな気分にさせたりしてくれるものだと思っていたので、いい気分転換として、時間がない時も少し散歩するなどしていました。
最後に3つ目の学習面について。僕が最も大切にしていたことは考え抜くことです。直前期はたくさん問題演習することも大切だと思いますが、そうでないときは基本解けるまで、あるいは分かるまでは時間無制限で徹底的に考え抜くように心がけていました。1問の数学の問題に1日を費やした時もありました。しかし、このようにして考え抜いた結果、分かるという状態に達したその経験や喜びは、自分の身体感覚の1部として自信と糧にかわり、問題を解く力となったような気がします。受動的にではなく、能動的に行動することが合格に繋がったように僕は思います。

早稲田大学
商学部
全トラック
山本多華 さん
( 大泉高等学校 )
2025年 現役合格
商学部
私は中学3年生で東進に入りました。部活動も忙しく、中学3年生、高校1年生のときは受講との両立ができなかった時もあり、何度も受講をサボったり自宅受講に変えたりしたことがありました。でも、高校2年生になって周りの友人も塾に入り始めたことでだんだんと自分の意識も変わり、受講を予定通りに進める、ずれてしまっても終わりは守るということを気にするようになりました。これは、高校3年生になった時にやっていてよかったなと思うことでした。
低学年の時からいたことで高校3年生のときは受講やその他のコンテンツに余裕を持って取り組むことができたのはとても良かったです。高校3年生は多くの人が短いという中で、私はもともと勉強が好きではなかったこともあって、すごく長く感じた1年でした。辛かったことも多かったです。辛かったエピソードを具体的に2つ紹介します。
まず、4月には部活も引退し、学校の授業も6限まで全部ある曜日は少なく、時間が今までよりも急に増えました。この時私はすでに心が折れそうでした。今まで時間がない中でいかに効率よくやるか考えていたのに、時間が増えて何をしたら良いかがわからなくなってしまったのです。でも、担任助手の方々や担任の先生、友人に相談して、弱点からやるべきことを逆算しながら自分なりのやるべきことを見つけることができました。だんだんとたくさんある時間にも慣れ、夏休みも乗り切ることができました。
でもやはり、1番辛かったのは冬休みです。過去問や演習で思ったように点数が取れず、すごく焦りました。担任助手の方々は直前に伸びるから、なんとかなるからと励ましてくれるけれど本当にそうなのかとすごく疑問でした。でも今思うと、本当になんとかなりました。努力していれば実は気づかない間にちょっとずつ伸びているんだろうなと思います。また、たくさん担任助手の方に相談したことでたくさん大丈夫と言ってもらえたおかげで、自信を持って試験に臨むことができたのもとてもよかったです。
結果的に第1志望にも合格することができ、応援してくれた家族、友人、東進の方々には本当に感謝しかありません。大学生活も一生懸命楽しみたいと思います。受験は本当に団体戦でした。たくさん周りの人を頼りながら悔いの残らないように努力してください!
低学年の時からいたことで高校3年生のときは受講やその他のコンテンツに余裕を持って取り組むことができたのはとても良かったです。高校3年生は多くの人が短いという中で、私はもともと勉強が好きではなかったこともあって、すごく長く感じた1年でした。辛かったことも多かったです。辛かったエピソードを具体的に2つ紹介します。
まず、4月には部活も引退し、学校の授業も6限まで全部ある曜日は少なく、時間が今までよりも急に増えました。この時私はすでに心が折れそうでした。今まで時間がない中でいかに効率よくやるか考えていたのに、時間が増えて何をしたら良いかがわからなくなってしまったのです。でも、担任助手の方々や担任の先生、友人に相談して、弱点からやるべきことを逆算しながら自分なりのやるべきことを見つけることができました。だんだんとたくさんある時間にも慣れ、夏休みも乗り切ることができました。
でもやはり、1番辛かったのは冬休みです。過去問や演習で思ったように点数が取れず、すごく焦りました。担任助手の方々は直前に伸びるから、なんとかなるからと励ましてくれるけれど本当にそうなのかとすごく疑問でした。でも今思うと、本当になんとかなりました。努力していれば実は気づかない間にちょっとずつ伸びているんだろうなと思います。また、たくさん担任助手の方に相談したことでたくさん大丈夫と言ってもらえたおかげで、自信を持って試験に臨むことができたのもとてもよかったです。
結果的に第1志望にも合格することができ、応援してくれた家族、友人、東進の方々には本当に感謝しかありません。大学生活も一生懸命楽しみたいと思います。受験は本当に団体戦でした。たくさん周りの人を頼りながら悔いの残らないように努力してください!

早稲田大学
先進理工学部
電気・情報生命工学科
土屋拓未 くん
( 城北高等学校 )
2025年 現役合格
先進理工学部
僕は、高1の3月ぐらいから東進に通い始めました。部活動は美術部に所属しており、週5日で活動をしていました。そんな忙しい中でも東進の動画授業などは、とても良いコンテンツだと思いました。僕は英語が苦手だったので、高1から高2までの間は高速マスター基礎力養成講座を継続してやり続けていました。この習慣のおかげで英語の基本的な知識は高3になる前までに完成し、また英語に限らず他の教科も含め、勉強をする習慣が早い段階でできていました。
東進でいいなと思ったコンテンツは、チームミーティングと志望校別単元ジャンル演習講座です。チームミーティングではチームメンバーと切磋琢磨しあいながら、自分も他のメンバーに遅れを取らずに最後まで勉強をすることができました。
また志望校別単元ジャンル演習講座では、自分の苦手な分野を中心的に演習をすることができ、ほかの受験生との差を埋めることができました。東進に高3ではなく高1ぐらいから入学することによって、早期に受験に対する意識を高めることができました。この意識があるかないかで努力量が大きく異なっていたと思います。模試は早いうちからたくさん受けることをおすすめします。なぜなら慣れることも大事ですが、自分が今どの立ち位置にいるのかを分析でき、長い時間をかけて勉強法や勉強すべき科目などを分析することができるからです。
受験はほとんどの人が避けては通れない道ではありますが、志望校合格のために努力をするという姿勢は今後の大学生活だけでなく、社会に出た時にも役に立つと僕は信じています。
東進でいいなと思ったコンテンツは、チームミーティングと志望校別単元ジャンル演習講座です。チームミーティングではチームメンバーと切磋琢磨しあいながら、自分も他のメンバーに遅れを取らずに最後まで勉強をすることができました。
また志望校別単元ジャンル演習講座では、自分の苦手な分野を中心的に演習をすることができ、ほかの受験生との差を埋めることができました。東進に高3ではなく高1ぐらいから入学することによって、早期に受験に対する意識を高めることができました。この意識があるかないかで努力量が大きく異なっていたと思います。模試は早いうちからたくさん受けることをおすすめします。なぜなら慣れることも大事ですが、自分が今どの立ち位置にいるのかを分析でき、長い時間をかけて勉強法や勉強すべき科目などを分析することができるからです。
受験はほとんどの人が避けては通れない道ではありますが、志望校合格のために努力をするという姿勢は今後の大学生活だけでなく、社会に出た時にも役に立つと僕は信じています。